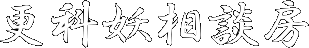
見える世界 * 壱
うちに私の友達がお泊まりに来ることになったのは、私が小学校四年生ぐらいのことだった。そろそろ幽霊とか妖怪とかを信じなくなる年頃。届くんは六年生で、“そういうの”たちのことをますます口にしなくなっていて、学校でもちょっぴり孤立しているような時期だった。
お泊まり計画のメンバーに泊まるのはうちでいいの、と聞いたら、みんなそろって頷いた。
「だってユコちゃんちは大きいし」
「竹林の中にあるしね。一回お泊まりしてみたいなぁって思ってたんだ!」
「で、でも……」
うちにはいろんなのが出るよ、とも言えなくて、私は口ごもる。時々届くんを頼って、そういうのが来ることがあるのだ。それに、ただでさえそういうのが集まって来やすい土地柄。昨日も神棚のお供え物を盗んだ罰当たりに、届くんがお仕置きしたばかりだ。走り回った届くんは柱に頭をぶつけてこぶをこさえた。目が見えないのに届くんは頑張り過ぎだと思う。
「ねーお願い。癒子みたいに、あんなに大きくて古い家に住んでる子なんてこの辺にはいないよ。夜に肝試しとかできそうだし、絶対楽しいよ。やろうよ!」
「でも……本当に何か出そうな気がするよ。うちのまわりってそういうのが集まってきやすいし」
私が言うと、みんな目をぱちくりして、それから笑った。
「そうだった」
「癒子って霊感あるんだよね……」
「でも、襲っては来ないでしょ?」
言われて、私はうーんと首を傾げた。確かに、今までそんなに危なっかしいのには会ったことないけど。というか、届くんが全部追い払ってくれた。大丈夫……なのかな。私だって、霊感があると言っても見えるわけじゃないし。聞こえるだけなのだ。
「えーと、あの、うちにはお兄ちゃんがいるし、届くんも……男の子と泊まるの、嫌じゃない?」
「だって、同じ部屋で寝るわけじゃないでしょ」
まあ、そうだけど。私はとりあえず言った。
「じゃあ、家族に聞いてみる」
「うん、お願いね」
にっこり笑って頼まれたら、私はもう断れなかった。
私が、うちであまりお泊まりすることに賛成できなかったのは、やっぱり届くんのことがあったからだ。届くんの「見える」「いる」発言は、今まで何度も変な顔をされる原因になってて、届くんはそれを気にしている。来年中学に入る時は盲学校にしようか、という話が出ているくらいだった。
私は嫌だった。県内には盲学校が二校しかなくて、しかもうちからはかなり遠いから、寮に住むことになるらしい。届くんと離れ離れなんで嫌だった。届くん自身は迷っているみたい。設備とかの面ではいい学校だろうけれど、そこに行ったって「そういうの」が見えるという能力が特殊なことに変わりはない。それに、仲のいい「そういうの」に文字を読んでもらったり道案内とかを頼めば、実際届くんにとって日常生活になにも支障はないのだ。それでとっても悩んでいるみたいだった。
その日も帰ったら、お兄ちゃんとお母さんがそのことで話をしていた。
「それでも、目が見えないっていう共通点を持った人が周りにいるのは、分かり合える人がいてあの子にとっても良いんじゃない?」
お母さんの声がする。お兄ちゃんが反論した。
「それは届の決めることだろ。俺は反対だな。今までだって十分よくやって来たじゃないか。授業だって、参加できないのは体育ぐらいだったろ」
「それはそうだけれど……チカくんだって知ってるでしょう、中学の子が一番不安定な時期よ。あの子みたいな特殊な子が、集団の中で上手くやっていけるかしら」
話は結局夕飯の席でも出た。私はお泊まりの件を聞くタイミングがつかめなくて、始終口をもぐもぐさせていた。見かねたお兄ちゃんが話をふってくれたけれど。
「癒子、何か言いたいことがあるなら言えよ」
「う、うん……」
あまり今言うべきじゃないような気がしたけれど、せっかくふってくれたので言うことにした。
「みんなでね、うちでお泊まりしようって話が出てるんだ」
「うちで? 誰がくるの?」
お母さんに聞かれて、私は友達の名前を挙げた。
「ちーちゃんとハルちゃんさっちゃん」
「いつ?」
「来週の土曜日」
「いいわよ」
あっさり言われて私は拍子抜けした。
「え、いいの?」
「お父さんが良いって言うならね」
お母さんがお父さんを見ると、お父さんは短く言った。
「雅親(まさちか)と届が良ければ」
「俺は全然良いぞ」
お兄ちゃんがこだわりなく言った。
「その、泊まりに来る奴らの中に男はいないんだろ」
「い、いた方が良かったかな」
届くんの遊び相手になってくれたかも。私が不安になって言うと、お兄ちゃんに軽くげんこつで叩かれた。
「癒子。兄貴の心配をそういう方向に解釈する妹がいるか」
「え? う、うん、ごめん」
「チカくんは兄バカねぇ」
お母さんとお父さんが苦笑していた。何なんだろう。
届くんは黙々とごはんを食べている。私は聞いてみた。
「届くんは、かまわない?」
「うん」
届くんの返事はもっと短かった。ううう、怒ってるかな。
「うるさいかもしれないよ。大丈夫?」
「うん。全然大丈夫」
怒ってないみたいだ。それで私はやっと安心した。
その夜、私が夜中にトイレに行くと、届くんが縁側のふすまを開け放って縁側に座っているのが見えた。ふわふわとその周りを飛んでいたのは、蛍。そういえば届くんがうちの玄関前に捨てられていたのも、蛍が飛び交う夜だったとか。
不思議な力をもった男の子と蛍っていう組み合わせが幻想的で、思わずもっと近くで見たくなって近づいたら、すぐに気付かれてしまった。
「癒子?」
足音だけで分かったみたい。やっぱり届くんはすごい。私はこそこそするのをやめた。
「うん。何してるの?」
「……妖が飛び回ってるんだ。綺麗だから、見てた。ここにいるよ」
届くんは言って、蛍を一匹手のひらにとまらせた。私は目をぱちくりした。
「妖? 私にも見えるよ」
「本当? どんな形に見える?」
「蛍の形。緑色に光ってる」
「大きさは?」
「すごくちっちゃい。長さが小指の爪くらい」
届くんは俯いた。
「じゃあ、やっぱり俺が見てるものと違うな」
私は後悔した。傷つけてしまった。
「俺には卵くらい大きいのが見える。光ってるのは同じだけど……この色は、緑っていう色なのかな」
届くんはそう呟くと、蛍っぽい妖を放した。私は何も言えなくて、どうしようもないから届くんの隣りに座る。そして、少し黙って考えた後、言った。
「……違ってて当たり前なんじゃないかな。私だって、自分の見てる色がお母さんやお父さんやお兄ちゃんと同じかどうか、分からないもん」
「そうなんだ……じゃあ、俺も泣き言言ってられないね」
届くんは呟き、顔を上げるとまた蛍の妖を眺め始めた。
それから、ぽつんと聞かれた。
「来週の土曜にお泊まりだって言ってたよね。お泊まりって、何をするの?」
「え? うーん、夜まで一緒にはしゃぐだけじゃないかな。ちーちゃんは肝試しをやろうって言ってたけど」
「そっか」
届くんは微笑んだ。
「楽しそうだね」
「届くんも楽しければ、もっと良いのにな」
私は思わず呟いた。届くんはすこし驚いた顔をしたけれど、それから嬉しそうに笑った。
「そう思ってくれるならそれで十分だよ」
「全然十分じゃないよ」
私はむくれたけれど、届くんは私の声の不満そうな声を聞いても表情を変えなかった。こうやって人の気持ちや好意を大事にしてくれる届くんが、私は大好きだ。
二人で縁側に並んで座って、蛍を眺めていると、こんな時間っていいなぁと思う。
「……ずっと一緒が良いのにな」
私は小さく小さく呟いた。届くんは、中学になったら行っちゃうのかな。そう思うとすごく寂しかった。
前へ ◆ 次へ
Background Photo by shape
Copyright © 2008 Kaduki Ujoh all right reserved.
|